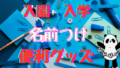夏に欠かせない食材といえば、やはりとうもろこし🌽
黄色い粒がぎっしり詰まった姿は見ただけで夏の風物詩を感じさせてくれますよね。
焼きとうもろこしや茹でとうもろこし、どちらもお祭りやバーベキューでは欠かせない一品です。
熱々のとうもろこしにかぶりつく瞬間、あの甘さと香ばしさが口いっぱいに広がり、夏の楽しさを一層感じさせてくれます。
今回はとうもろこしの旬やおいしい食べ方、保存方法などを調べていきますね。
- 【とうもろこし】旬の時期はいつ?
- 【とうもろこし】栄養成分は何がある?
- 【とうもろこし】選び方はどこを見る?
- 【とうもろこし】茹で時間はどのくらい?
- 【とうもろこし】保存方法は?冷凍も?
夏の風物詩なとうもろこし!
賢く選んで満喫しましょう!

【とうもろこし】旬の時期はいつ?

とうもろこしの旬は6月から9月です。
暑い季節に食べるイメージのあるとうもろこし。
初夏には九州や関西地方から始まり、盛夏には関東地方、そして夏の終わりには北海道へと、旬の波が北へ移動していきます。
このため、スーパーで売られているとうもろこしの産地表示を見ると、季節によってその産地が変わっていくのがわかるのでぜひ見てみてください。
これからの季節、スーパーでとうもろこしを手に取る際には、ぜひ産地にも注目してみてください。
【とうもろこし】栄養成分は何がある?

とうもろこしは世界三大穀類の1つです。
とうもろこしは夏の定番野菜として親しまれていますが、その美味しさだけでなく、栄養価も非常に高いことをご存知でしょうか?
とうもろこしにはさまざまな栄養成分が含まれており、健康維持に役立つ多くの効果があります。
- 炭水化物
- 食物繊維
それぞれ詳しく見ていきましょう!
【とうもろこし】栄養成分:炭水化物
炭水化物はエネルギー源として、体に重要な役割を果たしています。
炭水化物は大きく「糖質」と「食物繊維」に分けられます。
糖質は私たちが日常生活で活動するための主要なエネルギー源となります。
とうもろこしに含まれる糖質は、体内で素早くエネルギーに変換されるため、特に疲れた時や運動後に摂取すると、迅速にエネルギーを補給することができます。
このため、夏の暑い日やスポーツの後にとうもろこしを食べると、体が元気になる感じがするのです。
【とうもろこし】栄養成分:食物繊維
食物繊維は消化を助け、腸内環境を整える働きがあります。
特に不溶性食物繊維は、腸の蠕動運動を促進し、便秘の予防に役立ちます。
夏は汗をかくことが多く、水分の摂取も増えるため、腸内環境を整えることが重要です。
とうもろこしを食べることで、腸の健康を保ち、消化をスムーズにすることができますよ。
【とうもろこし】選び方はどこを見る?
新鮮で美味しいとうもろこしを選ぶにはいくつかのポイントがあります。
- 重さ
- ひげ
- 穴
- 皮
これのポイントを押さえれば、新鮮で美味しいとうもろこしを選ぶことができます。
では、詳しく見ていきましょう!
【とうもろこしの選び方】ずっしり重いもの
とうもろこしを選ぶ際に、重要なポイントの1つがその「重さ」です。
ずっしりと重みを感じるとうもろこしほど、内部の実がぎっしりと詰まっている証拠ですよ。
重量感のあるとうもろこしは、食べ応えがあり、ジューシーで美味しいものが多いのです。
まず、スーパーや市場でとうもろこしを手に取ったときに、その重さを確認しましょう。
軽く持ち上げてみて、しっかりとした重みを感じるものがベストです。
軽いとうもろこしは、中の実がスカスカしていたり、水分が抜けてしまっている可能性があります。
重いものほど、みずみずしくて新鮮な実が詰まっていることが多いので、重さは重要なチェックポイントですね。
【とうもろこしの選び方】ひげ
とうもろこしのひげは選ぶときにとても重要なポイントです!
- ひげがあるとうもろこし
- ひげが抜けないとうもろこし
- ひげがこげ茶なとうもろこし
ひげがなかったり、抜けたりしているものは、虫が食べている可能性が高いのです。
スーパーでとうもろこしを選ぶ際に、ひげの状態をしっかりとチェックすることが、美味しいとうもろこしを手に入れるための秘訣ですよ。
ひげが少ない、または完全にないとうもろこしを買って、いざ皮をむいたら中が虫食いだったという経験をしたことがある方はいませんか?
虫食いとうもろこしは驚きますが、実はそのとうもろこしが美味しい証拠でもあるのです。
虫が丸々太っているとうもろこしは、甘みが強く、美味しいとうもろこしであることが多いです。
しかし、家庭で楽しむためには、できれば虫食いは避けたいところですね。
ひげがこげ茶色になっているとうもろこしは、しっかりと熟しているサインですのでよく見てください。
【とうもろこしの選び方】横に穴が開いていないもの
横に小さな穴が開いているものは、虫が食べている可能性が高いです。
虫は皮を食べて内部の実まで侵入し、美味しい部分を食べてしまうことがあります。
どれだけ小さな虫でも、その強力なあごで皮を突破し、実にたどり着くのに驚きますよね。
皮の下の実が虫に食べられていると、その部分を切り取らなければならないので食べる部分が減ってしまいます。
虫が食べているところは黒くなっていますよ。

虫もおいしいの知ってるよね
【とうもろこしの選び方】皮の様子
とうもろこしを選ぶ際に、皮の様もポイントですよ。
- 緑色
- はち切れそうなくらいピーンと張っているもの
新鮮なとうもろこしの皮は、水分をたっぷりと含んでいるため、このような状態になります。
反対に、日が経つにつれてとうもろこしの皮はしなびてきて、色も薄くなり、最終的には白っぽくなってしまうんですよ。
この変化は、とうもろこしが収穫されてから時間が経過しているんです。
皮が張っているということは、とうもろこし自身がまだ十分に水分を保っているので、実もみずみずしく、甘さが際立ちます。
逆に、皮がしなびているとうもろこしは、収穫から時間が経っているため、糖度が落ちてしまい、風味も劣ってしまいますよ。
【とうもろこしの選び方】皮あり?なし?
とうもろこしを選ぶ際に、「皮あり」と「皮なし」のどちらを選ぶか悩みますよね。
皮ありのとうもろこしは、その鮮度を保つのでおすすめです。
皮があることで水分が逃げにくくなり、日持ちが良くなります。
冷蔵庫で保存する場合でも、皮がついていると乾燥を防ぎ、とうもろこし本来の甘みとジューシーさを保つことができます。
一方で、皮を剥く作業は力が必要で、手間がかかりますよね。
特に大量に調理する場合や、すぐに食べたい場合には、この手間が煩わしい!
そのため、忙しい日常の中での調理や、体力に自信がない方にとっては、皮なしのとうもろこしを選ぶ方が便利です。
ただし、皮がない分、水分が失われやすく、鮮度が落ちるスピードも速いので、購入後は早めに使い切ることをおすすめします。
【とうもろこし】茹で時間はどのくらい?
とうもろこしの調理時間は、調理方法によって違います。
| 調理方法 | 時間 |
|---|---|
| 茹でる | 10分~15分 |
| 蒸す | 10分くらい |
| 電子レンジ | 5分くらい |
茹でると一度にたくさんのとうもろこしを調理できますよね。
けどお湯を作るのが面倒だと、電子レンジや蒸す方が楽です。
では、それぞれの調理方法のポイントを伝授します!
【とうもろこしの調理方法】茹でる
茹でる方法は、とうもろこしの甘みを最大限に引き出す最も伝統的な調理法ですよね。
ポイントは、一番内側の薄皮を残して茹でることです。
この薄皮が水分を閉じ込める役割を果たし、とうもろこしの旨味と甘さを逃がさないようにします。
また、薄皮があることで、とうもろこしが均一に火が通りやすくなりますよ。
【とうもろこしの調理方法】蒸す
蒸す方法は、とうもろこしの自然な甘みと食感をしっかりと保ちながら調理するのに適しています。
蒸し器を使ってとうもろこしを約10~15分蒸すと、芯まで均一に火が通り、ふっくらとした仕上がりになります。
蒸す際にも皮を少し残しておくと、水分が逃げにくくなります。
蒸したとうもろこしは、茹でたものよりも甘みが凝縮されるため、より濃厚な味わいが楽しめます。
【とうもろこしの調理方法】電子レンジ
電子レンジを使う方法は、忙しい日常の中で手軽にとうもろこしを調理するのに最適です。
皮をむかずにそのまま電子レンジに入れるのがポイントです。
とうもろこし1本あたり、600Wで4~5分加熱します。
皮付きのまま加熱することで、とうもろこしの水分が逃げにくくなり、しっとりとした食感に仕上がります。
加熱後、皮をむくと、簡単に熱々のとうもろこしが楽しめます。
手間も少なく、鍋を使わないので洗い物も減り、ありがたいですね。
【とうもろこしの調理方法】いつが一番いい?
とうもろこしは、収穫直後が最も甘く美味しいとされています。
これは、とうもろこしの糖分が時間とともにデンプンに変わってしまうためです。
そのため、手に入れたらすぐに調理するのがベストです。
特に新鮮なとうもろこしは、その日のうちに調理することで、最高の甘さと風味を楽しむことができます。
【とうもろこし】保存方法は?冷凍も?
とうもろこしは、新鮮なうちに食べるのが一番美味しいですが、当日食べるのが難しい日もありますよね。
でも大丈夫!
保存方法を工夫すれば、ある程度の期間美味しさを保つことができるんです!
ここでは、冷蔵保存と冷凍保存の方法について詳しくご紹介します。
【とうもろこし保存方法】冷蔵保存
とうもろこしを冷蔵保存する場合は、皮つきのまま保存するのがポイントです。
皮が実を保護し、乾燥を防いでくれます。
そして、新聞紙にくるんで野菜室に立てて保存しましょう。
とうもろこしを立てて保存することで、水分が均一に保たれやすくなります。
この方法なら3日程度は新鮮さを保てますが、なるべく早めに調理することをおすすめします。
とうもろこしは時間が経つと甘みが減少してしまうので、早めに調理してその美味しさを楽しんでください。
【とうもろこし保存方法】冷凍保存
その日のうちに調理して冷凍が理想的です。
大量にとうもろこしを手に入れた場合や、一度に食べきれない場合には冷凍保存が便利です。
冷凍保存する際には、なるべくその日のうちに調理するのが理想的です。
まず、とうもろこしを茹でて冷ました後、実を芯から削ぎ落とします。
その後、削いだ実をフリーザーバッグに入れて空気を抜き、平らにして冷凍します。
この方法なら、とうもろこしの甘みと風味を保ちながら長期保存が可能です。
冷凍したとうもろこしは、そのままスープや炒め物、サラダなど様々な料理に使うことができ、とても便利です。
冷凍庫に常備しておけば、いつでもとうもろこしを楽しむことができますよ。

お弁当にも便利!
使いたい分だけパキッと割れるので、平らにして冷凍!

まとめ:【とうもろこし】旬はいつ?栄養価や選び方、調理と保存方法
今回はとうもろこしの旬やおいしい食べ方、保存方法などを調べていきました。
- 【とうもろこし】旬の時期は6月~9月!
- 【とうもろこし】栄養成分は炭水化物と食物繊維!
- 【とうもろこし】選び方は重さやひげ、穴を見るといい!
- 【とうもろこし】茹で時間は10分~15分!
- 【とうもろこし】手に入ったらすぐ調理!
とうもろこしは、「ひげ」が選ぶときに重要だというのは驚きですよね!
ポイントを押さえることで、より美味しいとうもろこしを手に入れることができますよ。
そのまま食べても、天ぷらにしても、スープにしてもおいしいのがとうもろこしです。
夏の味覚を最大限に楽しむために、ぜひこれらのポイントを活用してください♪
美味しさを最大限に引き出して、夏を楽しみましょう!